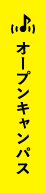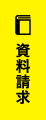eラーニング・プログラム第7回
第7回 音の高さ(その1)
音響を学ぶ者は、音の高さを周波数(単位はHzヘルツ)で感じ、表せるようにならなければなりません。
音芸では、「聴能形成」という授業と、その教材CD「聴能トレーニング」を通じて、
音芸生たちに「音程を周波数で感じる能力」を身につけてもらっていますので、皆さんにもその能力は身に付きます。
今日は、その前提として必要な、「音の高さ」に関する基礎知識を学んでいただこうと思います。
<人間の可聴周波数帯域>
健康な成人が音として認識できる周波数は、20Hz〜20,000Hz(=20kHz)とされています。
(この数字もそうですが、赤文字部分は全て音響関係者にとっては常識中の常識なので覚えてください)
音が、空気中を振動して伝わる波=音波 である、ということは、これまでも理科の授業で習ったかと思います。
20Hzの音というのは、1秒間に空気中を20回振動しながら我々の耳に伝わる音です。
<音の波長と可聴周波数帯域の関係性>
音は、(気温が摂氏15℃で気圧が1気圧という条件のもとでは)340m/sec,
つまり毎秒340mの速さで伝わるので、340m進む間に20回振動する(20個の波がある)のが20Hzの音だ、
とも言い換えることができます。
ということは、一つの波の長さは、340m/20=17mということになります。
この一つの波の長さのことを「波長」と呼びます。
音波の波長が17m以上になると、人間はそれを「音」として認識できなくなる、と言うこともできるし、
毎秒の振動数が20回未満の音は、人間には聞こえない、とも言うことができます。
また20kHz(=20,000Hz)の音は、1秒間に空気中を2万回振動しながら我々の耳に伝わります。
20kHzの音の波長は、340m/20,000=0.017m=1.7cm(17mm)ということになりますね。つまり、
音波の波長が1.7cm以下になると、人間はそれを「音」として認識できなくなる、と言うこともできるし、
毎秒の振動数が20,000回より多い音は、人間には聞こえない、とも言うこともできるわけです。